子どもの教育資金がどれくらい必要なの?
幼稚園から大学までの費用はどのくらい?
公立と私立で費用にどれくらい差があるの?
教育資金を効率よく準備する時期や方法って?
そんなお悩みありませんか?
教育資金の準備は、子どもの未来を守る上で大切なステップ。
しかし、公立・私立によって費用は大きく異なり、タイミングや方法を誤ると家計に負担をかけることも。
本記事では、『教育資金はいくら必要か?』をテーマに、幼稚園から大学までの費用や準備のコツを解説します。
この記事を読んでわかること
- 公立・私立別に必要な教育資金の平均額
- 教育費の内訳(幼稚園、小学校、中学校、高校、大学ごとの費用)
- 教育資金を準備する際のポイントや方法(学資保険や貯蓄の活用)
- 教育資金の準備を始める最適なタイミング
- 家計に負担をかけずに教育費を計画するコツ
この記事を読むことで、具体的な目安と無理のない計画方法が分かります!
今日から賢く備えましょう!
\ママにおすすめ!子育てや教育資金でお金に迷ったらプロに相談/
目次
教育資金はいくら必要?我が子の未来を守るための計画方法とは
教育資金はいくら必要?公立・私立別に徹底解説

子どもの教育資金を考える際、多くの親が気になるのは「公立と私立ではどのくらい費用に差があるのか」という点です。
特に家計を見直すタイミングで、「教育資金はいくら必要なのか」を明確にすることはとても重要です。
ここでは、文部科学省のデータをもとに、公立と私立それぞれの教育費の平均額を詳しく見ていきましょう。
出典:文部科学省『令和3年度子供の学習費調査』
幼稚園から高校までの教育費
まず、幼稚園から高校までの教育費の目安です。
文部科学省の調査によれば、以下のような差があります。
幼稚園~高校 教育費目安
- 公立の場合
幼稚園から高校までの教育費は、トータルで約500万円程度と言われています。これは授業料だけでなく、給食費や教材費、学校行事の費用などを含んだ金額です。 - 私立の場合
私立の幼稚園から高校まで通った場合の教育費は、平均で約1,800万円に達します。特に私立中学校や高校では授業料が高く、学外活動の費用も加算されることが要因です。
大学進学時にかかる費用
次に、大きな負担となるのが大学進学時の費用です。
公立と私立で次のような差があります。
大学進学費用
- 公立大学
初年度の費用は約80万円程度(授業料や入学金を含む)です。
その後、年間の授業料は平均約54万円とされています。 - 私立大学
文系の場合、初年度費用は約120万円~150万円。理系になるとさらに費用がかさみ、年間約200万円近くになるケースもあります。
また、自宅から通えない場合は、生活費や家賃も追加で必要になるため、1年間でさらに100万円以上の出費を想定しておく必要があります。
公立と私立で必要な教育資金の合計
これらをトータルすると、子どもが大学まで進学した場合の教育費は以下の通りです。
- 公立の場合:約1,000万円
- 私立の場合:約3,000万円
もちろん、子どもが選ぶ進路によって変動しますが、早めに教育資金の目安を立てておくことで、将来の不安を減らすことができます。
子供の教育資金のプランニングをしました。総額いくら必要でどのような方法で貯めるのか。毎月いくら貯金すればOKなのかが明確になりました。
— しょーやん (@sinn_shoyan) September 23, 2021
「教育資金はいくら必要?」と聞かれると、公立か私立、大学進学後の生活スタイルによって大きく異なることがわかります。
最初に大まかな金額感を把握し、それに基づいて計画を立てることが、家計に無理なく教育資金を準備する第一歩です。
次に、この教育資金を効率よく準備する方法について解説していきます。
教育資金の内訳とは?幼稚園から大学までの平均費用

教育資金を計画するには、具体的にどの段階でどのくらいの費用が必要になるのかを知ることが大切です。
まずは幼稚園から大学までの費用の内訳を、公立・私立別に分けて詳しく見ていきましょう。
幼稚園の費用
幼稚園は、子どもが初めて教育を受ける大切なステージです。
- 公立幼稚園
年間平均費用は約22万円です。授業料が比較的安く、補助金制度を活用することでさらに負担を軽減できます。 - 私立幼稚園
年間平均費用は約53万円。授業料に加え、制服代や園独自のイベント費用が含まれるため、公立より高額になります。
小学校の費用
義務教育が始まる小学校では、授業料は無料ですが、教材費や給食費がかかります。
- 公立小学校
年間平均費用は約33万円。6年間通うと約200万円程度が目安です。 - 私立小学校
年間平均費用は約160万円。特に授業料や学校独自のプログラム費用が高額で、6年間では約960万円に上ります。
中学校の費用
中学校では、教育内容が高度化し、クラブ活動や修学旅行などの費用が増えます。
- 公立中学校
年間平均費用は約48万円で、3年間通うと約150万円程度です。 - 私立中学校
年間平均費用は約140万円で、3年間の総額は約420万円。部活動や施設維持費などの費用がかさむ傾向があります。
高校の費用
高校では、進路選択に応じた学習環境が整備され、費用も多様化します。
- 公立高校
年間平均費用は約50万円で、3年間で約150万円が目安です。 - 私立高校
年間平均費用は約130万円で、3年間では約390万円。公立より授業料が高いものの、奨学金や補助金を利用する家庭も増えています。
大学の費用
大学は教育費の中でも最大の出費となる部分です。
- 国公立大学
初年度費用は約80万円、4年間の総額は約250万円~300万円が平均です。 - 私立大学
文系の4年間総額は約400万円~500万円、理系では約600万円~800万円に達することもあります。医学部や薬学部ではさらに高額です。
また、自宅外通学の場合、生活費や家賃で年間100万円以上の追加費用が発生します。
以上をまとめると、以下の通りです。
教育費の総額目安
- 公立のみ(幼稚園から大学まで):約1,000万円
- 私立のみ(幼稚園から大学まで):約3,000万円
- 公立・私立混合(私立中学・高校、国公立大学の場合):約2,000万円~2,500万円
教育資金の内訳を具体的に知ることで、計画的に準備を進めることができます。
公立か私立か、どの段階で選ぶかによって必要な金額は大きく変わります。
次に、これらの教育資金を効率よく準備するための方法を紹介します。
教育資金を効率よく準備する方法3選

教育資金の必要額が分かったら、次はどのように計画的に準備していくかを考える番です。
早めに対策を始めることで、将来の負担を軽減できます。
ここでは、効率的な教育資金の準備方法を3つ紹介します。
教育費専用の貯蓄口座を作る
まず最初に取り組むべきは、教育資金を目的とした専用の貯蓄口座を作ることです。
家計費と教育費を分けて管理することで、貯蓄の進捗を把握しやすくなります。
また、教育費専用の口座を設定しておくことで、他の支出に使ってしまうリスクを減らせます。
ポイント
- 月々の目標額を設定し、自動積立で確実に貯める。
- 家族構成や教育の選択肢に応じて貯蓄額を見直す。
学資保険を活用する
学資保険は、教育資金を計画的に準備する手段として多くの家庭で利用されています。
特に、一定の条件を満たせば返戻率が高くなる商品を選ぶことで、効率よく資金を積み立てることが可能です。
また、保険のため万が一の際にも備えられる点がメリットです。
ココがおすすめ
- 契約時に設定した年齢でまとまった金額を受け取れる。
- 万が一の際も、保険料の支払いが免除される場合がある。
ただし、返戻率や解約時のペナルティには注意が必要です。
加入前には複数の保険商品を比較検討しましょう。
積立型の投資信託を始める
低金利時代の現在、貯蓄だけで教育資金を準備するのは効率が悪い場合もあります。
そこで注目されるのが、積立型の投資信託です。
毎月一定額を投資し、長期的に資産を増やす方法で、つみたてNISAやiDeCoなど、税制優遇のある制度を活用することでさらに効率的に資金を運用できます。
ココがおすすめ
- 少額から始められ、家計に負担をかけずに運用可能。
- 長期運用で複利の効果が期待できる。
投資には元本割れのリスクが伴うため、安定した商品を選び、無理のない範囲で運用を行いましょう。
教育資金の準備は、早めに計画を立てることが成功のカギです。
貯蓄口座の開設や学資保険、投資信託の活用など、自分の家庭に合った方法を選び、コツコツと積み立てていきましょう。
次に、具体的なシミュレーション例を通じて、さらに計画的な資金準備のポイントを解説します。
教育資金のシミュレーション:必要額を明確にする方法

教育資金を計画的に準備するためには、具体的な金額をイメージすることが大切です。
ここでは、実際のケースに基づいたシミュレーション例を紹介し、必要額を明確にする方法を解説します。
公立校と私立校で大きく異なる費用
教育資金は、通わせる学校の種類や進路によって大きく変わります。
たとえば、公立校は授業料が比較的低く抑えられるのに対し、私立校では授業料以外にも寄付金や施設費などの費用がかかることが一般的です。
例:高校3年間の教育費(1人あたり)
- 公立校:平均約120万円
- 私立校:平均約290万円
このように、同じ3年間でも約2倍以上の差が生じるため、進路を想定して準備することが重要です。
習い事や塾代も考慮する
学校以外の費用も忘れてはいけません。
特に習い事や塾代は家庭ごとに大きく異なります。
たとえば、中学受験を目指す場合、塾代だけで年間50万~100万円かかることも珍しくありません。
シミュレーション例:年間の教育費
- 習い事(月5,000円 × 12カ月):60,000円
- 塾代(年間100,000円):100,000円
- その他教材費:20,000円
合計:年間約18万円
大学進学時の費用を見据える
大学進学は、教育資金の中でも特に負担が大きい部分です。
特に私立大学や一人暮らしの場合、年間100万円を超える学費や生活費が必要となります。
例:大学4年間の費用(私立大学・文系)
- 学費:年間約130万円 × 4年 = 約520万円
- 生活費:年間約100万円 × 4年 = 約400万円
合計:約920万円
この金額は家庭にとって非常に大きな負担となるため、分割で準備できる仕組みを作ることが重要です。
シミュレーションツールを活用しよう
教育費の計画を具体的にするためには、専用のシミュレーションツールを活用するのも一つの方法です。
たとえば、ファイナンシャルプランナー(FP)への無料相談を利用すれば、子どもの進路や家計状況に合わせた詳細な計画を作成できます。
FP相談でわかること
- 子どもの教育費総額
- 効率的な貯蓄・運用方法
- 家計のバランスを崩さない貯蓄計画
無料で何度でも相談可能なサービスを利用すれば、プロの意見を参考にしながら無理のないプランを立てられます。
教育資金を効率よく準備するには、必要な金額をシミュレーションして明確にすることが不可欠です。
公立校か私立校、習い事や塾代、大学進学の選択肢によって費用は大きく異なります。
現状の家計を見直しながら計画を立てるためにも、FPなどの専門家の力を借りて将来に備えるのがおすすめです。
次に、実際にファイナンシャルプランナーへ相談するメリットとその活用方法について詳しく紹介します。
教育資金を無理なく準備するための具体的な方法
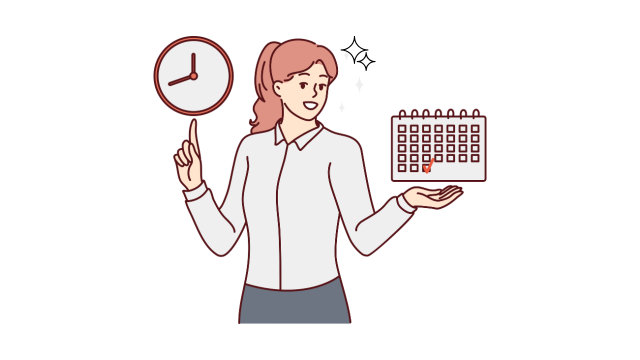
教育資金を効率的に準備するには、無理のない貯蓄計画や投資を活用することが重要です。
ここでは、誰でも取り組みやすい具体的な方法を3つ紹介します。
家計を見直し、余剰資金を確保する
教育資金を準備する第一歩は、家計の現状を把握することです。
毎月の収支を記録し、無駄な出費を洗い出しましょう。
家計見直しポイント
- サブスクリプションサービスや保険の見直し
- コンビニや外食の頻度を減らす
- 電気・ガス・水道の契約プラン変更
たとえば、月に5,000円の節約を実現できれば、年間で6万円を教育資金に回せます。
この積み重ねが将来の大きな安心につながります。
教育費にしろ老後資金にしろ、とにかく資産形成は「いつまでにいくら必要だから毎月いくら貯めて、そのために予算は大体いくらにして」というのを決めるのが王道のやり方で、今の生活費についてたまに見直すのも普通だと思うんだけどなぁ。じゃないと貯まらないし。
— おふ (@ofutooo_n) January 16, 2025
児童手当や給付金を活用する
日本では子どもの成長を支援するために、児童手当や給付金が支給されています。
これを教育資金の貯蓄に充てることで、効率よく資金を確保できます。
児童手当の例(1人あたり)
- 3歳未満:月額15,000円
- 3歳以上~中学生:月額10,000円(第3子以降は15,000円)
この金額をそのまま貯金に回せば、18歳までに約200万円以上の資金を確保することが可能です。
学資保険や積立投資を検討する
教育資金を確実に準備するためには、学資保険や積立型の投資信託を活用するのも効果的です。
学資保険の特徴
- 満期時にまとまった資金を受け取れる
- 保険料の支払いが途中で困難になった場合も一部保証がある
積立投資信託の特徴
- 長期で運用することで元本を超えるリターンを狙える
- リスク分散が可能で、少額から始められる
特に積立NISAやジュニアNISAなどの税制優遇制度を利用すれば、運用益にかかる税金を抑えられます。
これにより、効率的に教育資金を増やせます。
ファイナンシャルプランナーに相談する
教育資金の準備に不安を感じる方は、ファイナンシャルプランナー(FP)への相談を検討してみましょう。
専門家のアドバイスを受けることで、自分では気づけなかった家計の改善点や適切な運用方法が見えてきます。
FP相談で得られるメリット
- 無駄な出費のカットと効率的な貯蓄方法の提案
- 子どもの進路に合わせた教育費計画の立案
- リスクを抑えた運用プランの作成
無料で何度でも相談できるFPサービスを活用すれば、プロの知識を最大限に活かしながら計画を立てられます。
教育資金の準備は、早めに始めるほど効果が高まります。
まずは家計を見直し、余剰資金を確保することから始めましょう。
そのうえで、児童手当の活用や学資保険、積立投資信託など、自分に合った方法を選んで効率よく資金を貯めることが大切です。
さらに、プロの力を借りたい方は、無料のFP相談を活用することで、安心して未来に備えることができます。
まとめ
子どもの教育資金は、計画的に準備することで安心感が得られます。
本記事では、必要な金額の目安や効率的な準備方法を解説しました。
まずは家計を見直して余剰資金を確保し、児童手当や学資保険、積立投資などを活用して計画的に貯めることが重要です。
不安がある場合は、無料のファイナンシャルプランナー相談を活用するのもおすすめです。
未来のために、今できる一歩を踏み出し、子どもの夢を叶えるための準備を始めましょう。
\無料で何度でも!子育てや教育資金でお金に迷ったらプロに相談/

