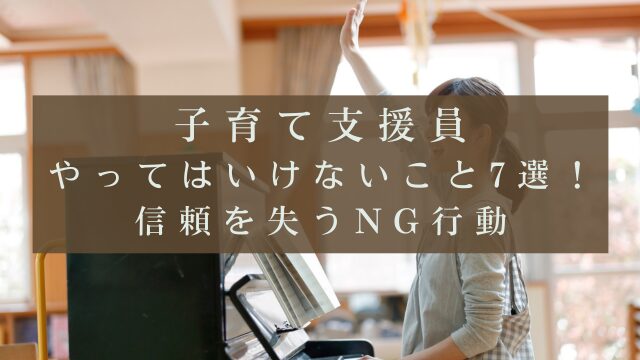子育て支援員は「子どもが好き」という気持ちだけでは通用しない場面が多くあります。
現場では、保育士や保護者との信頼関係が何よりも大切。
しかし、ちょっとした言動が誤解を招き、信頼を損なってしまうことも…。
この記事では、子育て支援員がやってはいけないこと7選と、信頼される支援員になるためのポイントを解説します。
これから支援員を目指す方や、現場で不安を感じている方はぜひ参考にしてください。
目次
子育て支援員やってはいけないこと7選!信頼を失うNG行動とは?
はじめに:子育て支援員の役割と責任

子育て支援員の役割と責任とは
子育て支援員は、保育士の補助として保育現場に関わり、子どもの健やかな成長を支える存在です。
直接的な保育だけでなく、環境整備や食事補助、見守りなど幅広いサポートが求められます。
ただし、保育の「主役」ではないため、行動や発言には慎重さが必要です。
補助的立場だからこそ、信頼される態度や行動が何より重要です。
こちらもCHECK
-
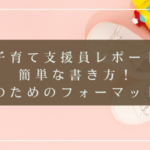
-
子育て支援員レポート例文集!失敗しない書き方の5ステップ
続きを見る
なぜ「やってはいけないこと」を知る必要があるのか?
現場での小さなミスや不用意な言動が、子どもや保護者との信頼関係に大きく影響を及ぼすこともあります。
特に、支援員の立場で行うNG行動は「越権行為」とみなされる可能性も。
やってはいけない行動を事前に知っておくことは、トラブル回避や信頼構築の第一歩です。
子育て支援員やってはいけないこと7選

子育て支援員やってはいけないこと①保育士の指示を無視して独断で行動する
支援員はあくまで「サポート役」。
保育方針や細かい対応は保育士が決定します。
独断で子どもを外に連れ出したり、遊びのルールを勝手に変えたりする行為は信頼を大きく損なう原因に。
必ず保育士の指示を仰ぎましょう。
子育て支援員やってはいけないこと②子どもへの強い叱責・感情的な対応
支援員が子どもに対して強い口調で叱ったり、感情的に対応したりするのはNGです。
しつけや注意は保育士の役割であり、支援員が感情をぶつけるのは逆効果。
冷静で優しい対応を心がけることが信頼につながります。
子育て支援員やってはいけないこと③保護者に勝手に助言・情報提供する
送り迎えの際などに、保護者へ直接子どもの様子を伝えたり、助言をしてしまうのは避けましょう。
子どもの状態や保育方針は保育士が一貫して対応すべきこと。
支援員が主導で話すことは避け、報告は必ず保育士に任せるのが基本です。
子育て支援員やってはいけないこと④「自分のやり方」を押し通そうとする
過去の経験や持論に基づいて、自分流のやり方を現場に持ち込もうとするのも要注意。
施設ごとに保育方針や運営ルールが異なるため、柔軟に合わせる姿勢が大切です。
独自のやり方を主張するより、チームワークを優先しましょう。
子育て支援員やってはいけないこと⑤指示が分からないまま行動する
「忙しそうだから」と確認を遠慮して曖昧なまま動いてしまうのは危険です。
誤解が事故やトラブルにつながることも。
分からないことは必ず確認する勇気が必要です。
不安な点はその場で聞くようにしましょう。
子育て支援員やってはいけないこと⑥報告・連絡・相談を怠る
子どもの体調の変化やトラブルを見つけたとき、すぐに保育士へ伝えないのは重大なミスにつながります。
支援員であっても、「報・連・相(ほうれんそう)」は必須。
見たこと、感じたことを適切に共有しましょう。
子育て支援員やってはいけないこと⑦子どもと「なれなれしく」なりすぎる
子どもと信頼関係を築くことは大切ですが、距離が近すぎるとトラブルの元に。
あだ名で呼んだり、タメ口で話したりすることは避け、適度な距離感と礼儀を保つことが求められます。
特に保護者が見ている場面では注意が必要です。
子育て支援員が信頼を得るための3つのポイント

子育て支援員が信頼を得るポイント①報連相の徹底で信頼関係を築こう
保育現場で最も重視されるのが「報告・連絡・相談」。
自分が見たことや気づいたことを正確に共有することを意識します。
すると、保育士との連携がスムーズになり、子どもたちにも安心感を与えることができます。
子育て支援員が信頼を得るポイント②保育士とのチームワークを意識する
支援員の仕事は単独では成り立ちません。
保育士との信頼関係を築き、「この人なら任せられる」と思われることが重要。
感謝の気持ちや柔軟な姿勢を忘れずに、日々のコミュニケーションを大切にしましょう。
子育て支援員が信頼を得るポイント③常に子どもの安全と成長を最優先に考える
迷ったときは、「この行動は子どもの安全・成長にとって適切か?」を基準に考えましょう。
そうすることで自然と正しい判断ができるようになります。
支援員としての本質的な役割を常に意識することが、信頼される第一歩です。
まとめ|子育て支援員として信頼される行動を心がけよう
子育て支援員として働く上で、NG行動を知っておくことはとても大切です。
知らず知らずのうちに信頼を失ってしまう前に、「やってはいけないこと」をあらかじめ理解し、意識して行動するようにしましょう。
現場では不安なこと、分からないことも多いはず。
そんなときこそ、「迷ったら確認・報告」を徹底することが大切です。
それが結果的にトラブル回避につながり、信頼される支援員への近道となります。